〔問合せ、質問はイエローページを参照〕
緊急時
感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の損傷、供給支障事故等の防止に留意して下さい。また、万一の対処法を確立しておいて下さい。
実験盤利用
実験盤の取扱い・接続に関しては、電気担当者(イエローページ参照)に事前にご相談下さい。
配線
1.
配線は、許容電流・耐電圧・耐熱・耐放射線等を考慮して下さい。
2.
今後設置するケーブルは原則として環境に優しいエコケーブルを使用して下さい。
(EM-CE…ケーブルはエコケーブルです。)
3.
詳細は「実験盤に接続するケーブルの太さについて」の項参照
4.
接地線は、原則として緑色を使用して下さい。
施工・点検
1.
機器及び材料の選定は、安全な電気用品のマークが標示されているものを使用して下さい。
2.
開閉器の「入」「断」は、無負荷状態で行って下さい。「入」(投入)操作は上流側から、「断」操作は下流側から行って下さい。
3.
電気機器の点検、改修等の作業は、停電作業とし活線作業は行わないで下さい。
4.
停電作業は、必ず検電し、必要な接地を行い、適切な感電防止器具(ヘルメット、手袋、耐電靴、ディスコン棒など)を使用して下さい。
5.
現場機器の作業は、遠隔操作機能を停止してから行って下さい。
6.
アーク溶接作業に使用する溶接ホルダー、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、移動式若しくは可搬電動機械器具に使用する感電防止漏電遮断器などの安全用具、安全装置についても使用開始前に点検を行って下さい。
警報
1.
高電圧若しくは大電流装置を運転するときには、必ず赤色警告灯を点灯して下さい。
2.
励磁中の磁石は、鉄製品を吸引し非常に危険なので注意して下さい。
保安
1.
器具コード、テーブルタップによる“たこ足配線”は行わないで下さい。
2.
電工ドラムの巻いたままの使用は、焼損につながりますので避けて下さい。
3.
接地が必要な電気機器は、確実に接地して下さい。また、接地線は切断してないか接地線の浮き上がりはないかなどについて、使用開始前に点検を行って下さい。
4.
ケーブルまたはコードの床上転がしは避けて下さい。やむを得ない場合は保護カバーをして下さい。
5.
故障した機器の使用は、感電等の事故につながりますので、実験機器は常に点検整備し正常な状態で使用して下さい。
実験盤の使用要領
1.
実験盤は、電気担当者が管理しております。実験機器を接続する場合は、必ず電気担当者の承諾を得て接続して下さい。
2.
実験盤は下記の事項に留意して使用して下さい。また、実験盤に新たに大容量機器を接続するときは、電気担当者に連絡して、指示を受けて下さい。
(1)
実験盤の異常
|
事項 |
状態 |
処理 |
|
ブレーカの過熱 |
熱さを感じる |
電気担当者へ連絡する |
|
ブレーカの異常音 |
うなり(少し離れても聞こえる)、振動 |
〃 |
|
ブレーカの破損 |
ひび割れ、欠損がある |
〃 |
|
ブレーカの2次側 |
動かしてみて配線にゆがみがある |
〃 |
|
接続配線の異常 |
被覆の変色・過熱がないか |
〃 |
(2)
電気担当者は、2次側端子のゆるみ等について、少なくとも年1回以上使用前点検を実施して下さい。
(3)
実験盤の2次側配線
1)
接続は、撚り線のケーブルを使用して下さい。
2)
ビニールコードは使用しないで下さい。
一般にビニールコードは、差し込みプラグを使用し、コンセントより電源を取る小容量機器に使用します。
3)
負荷電流が20A以下の場合でも、2mm2以上のケーブルを使用して下さい。キャプタイヤケーブルは3.5 mm2以上のケーブルを使用して下さい。
4)
ブレーカへの接続は、圧着端子を使用して下さい。
5)
接続ケーブルは、結束棒又はブラケットに固定して下さい。
6)
1つのブレーカ端子より分岐できる配線は2本までとします。
7)
接続ケーブルには、負荷機器名を記入した標示札(またはテープ)を取り付けて下さい。
実験盤に接続するケーブルの太さについて
ケーブルの太さの選定は最初の太さ以上のサイズを選定すること
(参考法令:電気設備の技術基準の解釈第170条及び第171条)
ケーブルの許容電流
(低圧EM−CE3またはEM―CE−Tケーブル、低圧CV3芯またはCV−Tケーブル)
|
サイズ (mm2) |
許容電流(A) |
サイズ (mm2) |
許容電流(A) |
||
|
EM−CE3芯 CV3芯 |
EM−CE−T CV−T |
EM−CE3芯 CV3芯 |
EM−CE−T CV−T |
||
|
2 3.5 5.5 8 14 22 38 |
23 33 44 54 76 100 140 |
86 110 155 |
60 100 150 200 250 325 |
190 260 340 410 470 555 |
210 290 380 465 535 635 |
EM−CEは600V架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブルを、EM―CE−Tは同単芯3こ撚りケーブルを示す。
CVは600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブルを、CV−Tは同単芯3こ撚りケーブルを示す。
1.実験盤から負荷に接続する場合の実験盤定格電流(ブレーカトリップ電流)とケーブルの最小太さ
(1)
実験盤2次側端子に負荷ケーブルを1本接続する場合
実験盤遮断器
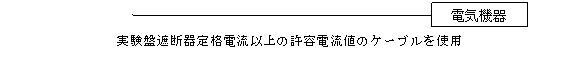
1本接続負荷ケーブルサイズ早見表
(低圧EM−CE3芯またはEM−CE−Tケーブル、低圧CV3芯またはCV−Tケーブル)
|
許容電流 (A) |
サイズ (mm2) |
許容電流 (A) |
サイズ (mm2) |
|
20 30 50 60 75 100 150 200 225 |
2 3.5 8 14 14,
T14 22,
T22 60,
T38 100,
T60 100, T100 |
300 400 500 600 700 800 1000 1200 |
150, T150 200, T200 325, T250 T325 T150×2 T200×2 T250×2 T325×2 |
(2)
実験盤2次側端子に負荷ケーブルを2本接続する場合
(やむを得ない場合は2本まで接続できるが、2本接続した場合は実験盤遮断器のケーブルに条件を満たしている旨を表示する。)
子遮断器または機器保護遮断器 実験盤遮断器
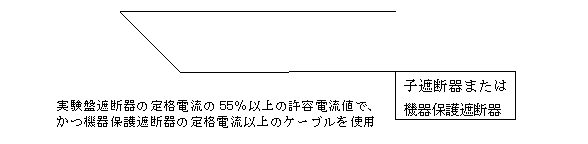
2本接続負荷ケーブルサイズ早見表
(低圧EM−CE3芯またはEM−CE−Tケーブル、低圧CV3芯またはCV−Tケーブル)
|
許容電流 (A) |
サイズ (mm2) |
許容電流 (A) |
サイズ (mm2) |
|
20 30 50 60 75 100 150 200 225 |
2 2 3.5 3.5 5.5 14 22,
T14 30,
T22 38,
T38 |
300 400 500 600 700 800 1000 1200 |
60,
T60 100,
T100 150,
T100 150,
T150 200,
T200 250,
T200 325,
T325 T150×2 |
感電防止のための注意
1.
高電圧や大電流の通電部ないし帯電部に誤って接近・接触することがないよう絶縁物で遮蔽もしくは、その近くの場所へは立ち入れないよう柵を設け、さらに危険区域である旨を表示して下さい。
2.
電気機器の通電部ないしは帯電部へ直接触れることが必要になった時は、電源を切り検電器で機器が通電・帯電状態でないことを十分に確認してから作業を行って下さい。更に、接地棒により、その部分を必ず接地した状態にして、作業を進めて下さい。
3.
むやみにインターロックを外して作業しないで下さい。(特にドアー開閉等)
4.
作業する電気機器の配電盤のブレーカを切ると共に作業中であることの表示を行って下さい。
5.
電気機器からの漏洩電流を避けるため、付着したゴミや油を取り去って、機器とその周囲を清潔に保って下さい。
6.
高電圧や大電流をともなう実験は、単独ですることを避け、2人できれば3人以上で行って下さい。
7.
万一、事故が発生した場合は迅速に電源を遮断できるように、配電盤の位置と操作法を常に念頭に入れておいて下さい。
8.
感電により転倒した場合でも、できるだけ安全確保のため、平常から実験室の状態に気をつけて下さい。
なお、実験の際は作業し易くまた余分なひれなどのない服を着用し、必要に応じて、安全帽、ゴム手袋、ゴム靴や絶縁台等を適宣使用して下さい。ゴム手袋の使用にあたっては、ごく小さい孔もあいていないことの確認を励行して下さい。
軽微な電気工事のための注意
1.
ユーザーは自分で使用する装置(負荷)の電気的な特性、定格電圧、定格電流を把握して下さい。
2.
分電盤内で負荷に必要な電圧、電流を分岐するブレーカを選定する。ブレーカの定格電流の決定は負荷及び、負荷までの電線を保護するために重要です。分電盤内のブレーカを使用する際は、配線に対する配慮ならびに、所謂たこ足配線防止による安全確認のため、使用責任者の許可が必要です。
3.
分電盤から負荷までの電流は負荷の定格電流が流せることが必要であるとともに以下のことに注意して下さい。
(1)
裸電線は使用しないで下さい。
(2)
600V絶縁電線を選定して下さい。
(3)
種類はこの配線の場合はキャブタイヤケーブルを使用して下さい。
(4)
負荷の装置が移動しない場合他のケーブル選定も可能です。例えばCVケーブル。キャブタイヤケーブルは乾燥した場所で、一種キャブタイヤケーブルは300V以下(溶接用移動電線相当品であり使用しない方が良い)。二種、三種、四種キャブタイヤケーブル600Vまで使用できます。
(5)
負荷までのケーブルは出来る限り短く途中に接続点のないものを使用して下さい。
(6)
途中で電線を接続する場合(導体断面積8平方ミリメートル以下)は、接続器具(ソケットとプラグ又は接続ボックス)を使用する。太いキャブタイヤケーブルについては圧着接続スリーブ等を使用し接続することが許されます。この接続で注意することはケーブルの抵抗値を増加させないこと、ケーブルの強度を二割以上低下させないこと、絶縁強度を低下させないことです。
(7)
分電盤から負荷までの配線はできる限り短くし、やむを得ずケーブルを固定する場合は単にその移動を防止する程度にとどめる。ケーブルがドアーや壁を貫通して永続的に使用するような配線工事は電機工事会社に委託すること。
4.
接地の配線は装置の鉄枠(シャーシー、モーター)と大地とを電気的に同電位とし、漏電や故障の際の操作者の感電を防止し、また漏電ブレーカが確実に動作するために必要です。
(1)
使用電圧が300V以下の装置はD種接地(接地抵抗100Ω以下)、300Vを超える場合はC種接地(接地抵抗10Ω以下)の配線が必要です。実際の設置配線は、分電盤の中にC種接地の端子が用意されているので、その端子と背内の鉄枠またはアース端子を電線で接続して下さい。
(2)
この時、使用する電線サイズは装置の定格電流に応じてJEC内線規定に示されているものを使用して下さい。