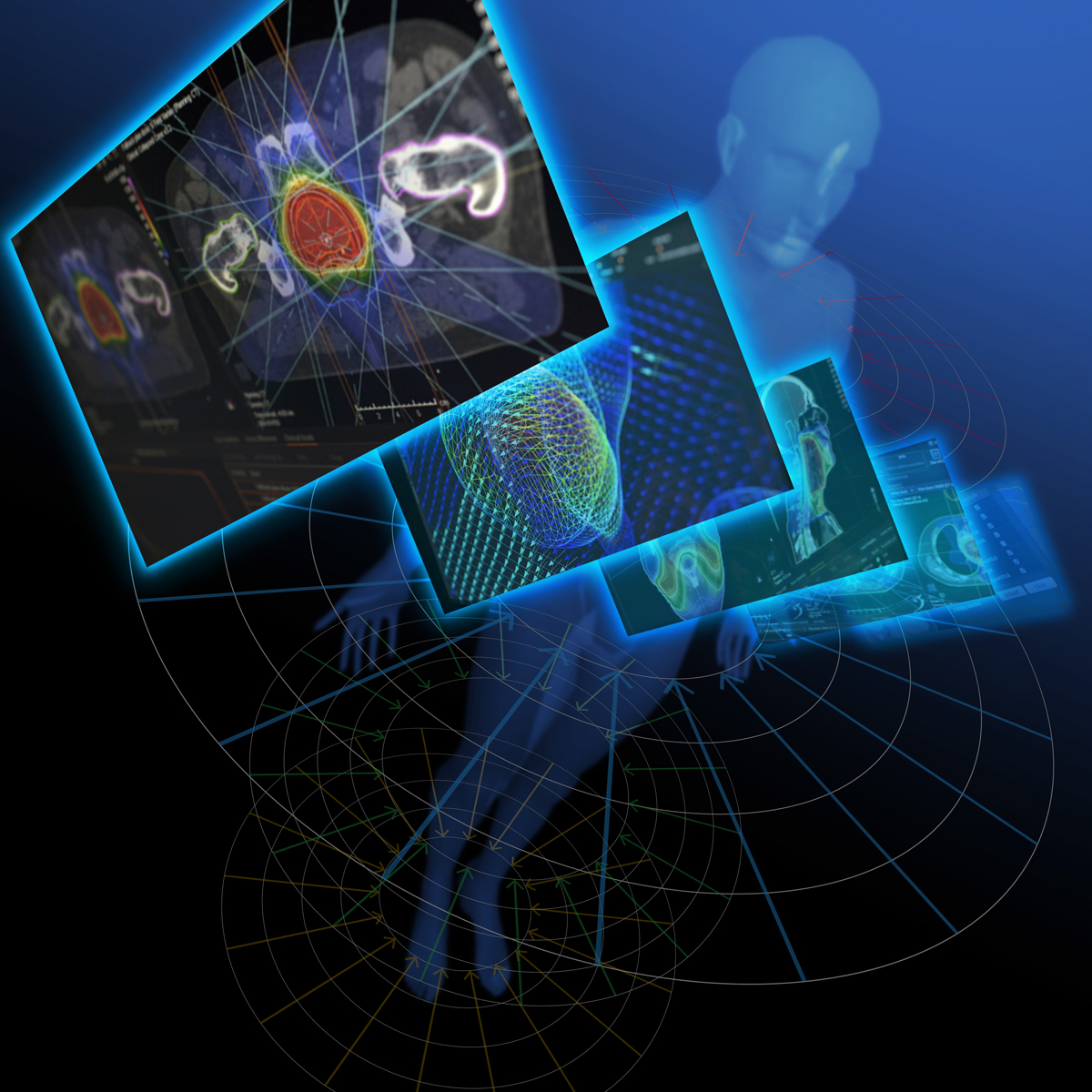基研研究会 放射線の生体影響解明への分野横断による挑戦
2019年5月(日時調整中) 京都大学基礎物理学研究所 研究棟 K206
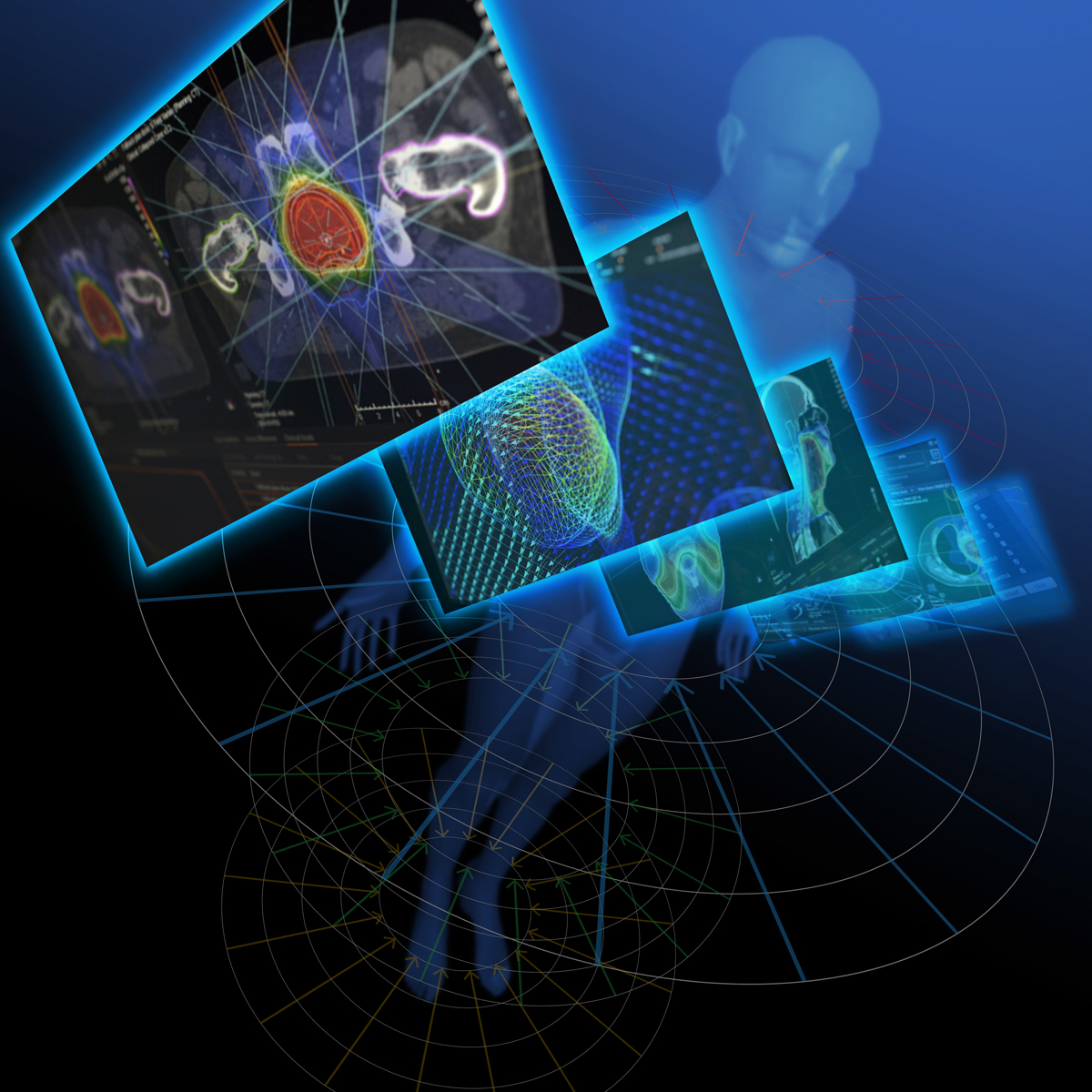
趣旨
-
放射線の生体影響、特に、低線量・低線量率の領域は、影響が小さく、実験で検出す
ることが困難であり、疫学的データも得にくいため、定量的な理解が難しい。そして、ほ
ぼ半世紀、LNT 仮説(確率的影響は、総被ばく線量に関して閾値がなく直線で増加すると
いう仮説)が放射線防護の指針となってきたが、これには、その後の膨大なデータの成果
が反映されていない。そして、近年、放射線医療や放射線利用、原子力エネルギーの活用
や放射性廃棄物処理などの課題と連動して、国際的に見直しが検討され始めている。
日本では、2011 年3 月11 日の東京電力福島第一原子力発電所事故以後、多くの科学者が、
放射線の生体影響の問題を深刻に受け止めた。物理学者も、放射線生物学という草創期に
は物理学者達が活躍していた分野に再び参入し、新しい数理モデルを提案し、様々な学会
から招待され、更なる成果を期待されている。また、放射線治療に対する関心の深まりか
2
ら、物理学会から医学物理へ進出する研究者が増加し、2003 年以来すでに70 名近い専門家
がこの方面で活躍している放射線の生体影響という課題の研究の歴史を辿ってみると、当
初から生物学と物理学との出会いがあった。遺伝学者マラー(1946 年ノーベル医学・生理
学賞)が、ショウジョウバエへのX 線誘発突然変異を発見したのは1927 年だった。自然
突然変異に加えて、人工的な突然変異が生じるというこの発見は、世界の科学者に衝撃を
与えた。「Physics and Genes: From Einstein to Delbruck」(“ Creating Physical Biology ”
Chapter 2)によると、この驚きはコペンハーゲンのボーア、シュレディンガー、デルブ
リュック達物理学者を大いに刺激し、「これこそ、生命の神秘を解くカギになる」と連日熱
い議論が戦わされた。特に、ボーアに触発されたデルブリュックは、1935 年にK.Zimmer(物
理) とN.T. Timofeeff(生物)の三者で、分野横断的連携の成果として、"On the Nature
of Gene Mutation and Gene Structure" (Three-Man Paper と呼ばれている)を発表した。
この仕事はワトソン、クリックによるDNA の発見を呼び分子生物学を誕生させ、Luria と
Delbruck の理論は生物物理学の誕生へとつながった。さらに、1946 年には、原子核物理学
者であったリーが「標的理論」という数理模型をLuria とDelbruck の理論を改良すること
で提唱し、放射線による細胞死の定式化が完成した。これは今も、放射線生物学の基礎方
程式となっている。
日本でも、放射線の生体影響の研究は、物理学と深いつながりがある。1923 年から数年
間ニールス・ボーアの下で研究に勤しんだ仁科芳雄は、1937 年理研サイクロトロンが稼働
するとすぐ、原子核研究室の村地孝一に中性子を生物に当てる実験を勧めた(Nature 140
(1937))。また、近藤宗平(京大理物理学科出身)は、広島原子爆弾投下後に京大原爆物
理調査班に学生として参加した1 人であり、核物理学から遺伝学・基礎医学に転身し、国
立遺伝学研究所室長、大阪大学教授を務めた日本での放射線物理学の創始者である。彼は、
「放射線を照射された物質の側に起こる物理的, 化学的, 生物的効果」、すなわち、放射線照
射過程(物理的) ⇒ 1 次反応(物理化学的) ⇒ 2 次反応(生化学的) ⇒生物のレスポンス(生物
的) という4 段階に焦点を当てた研究方針を打ち立てた。
その後、DNA は損傷するだけではなく修復効果があるという成果が出てきたが、残念なが
ら、これらを踏まえた放射線による生体への影響の定量化は行われていない。そこで、こ
れらの実績を踏まえて、蓄積された生物学的知見を整理し、様々なところに散らばる様々
な分野の研究者の実績を統合し、現段階の到達点と今後の課題を明確にし、分野横断的研
究を連携して進めることが望まれる。そして、さらに、放射線生物学や放射線医学の現状
と未来を展望し、新たに、飛躍的に展開していく道を開くというのがこの研究会の目的で
ある。
分野横断型の研究会を実施することは、この研究プロジェクトを遂行するにあたって最も
重要な部分である。これまで個々の分野で積み上げた研究を発展させ、生物学実験、分子生
物学・疫学のサイドに加えて物理・化学的アプローチも含めて、総合的にレビューを行い、
異分野の研究者が一定の共通認識の上に立って、今後の研究戦略を策定すること、加えて、
最近の成果を発表し合い、分野の壁を乗り越えて議論することが、今必要であると考える。
トップページに戻る