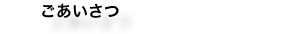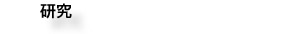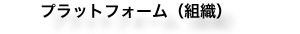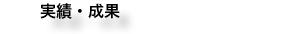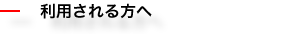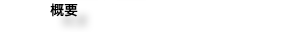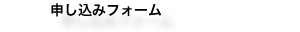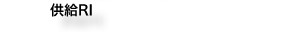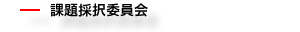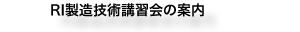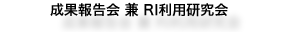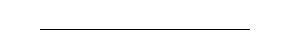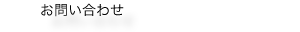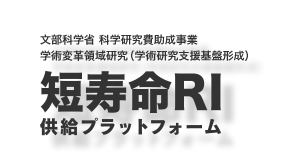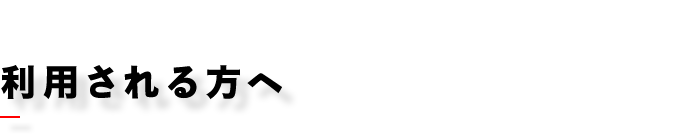
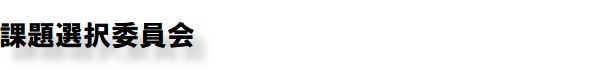
【課題選択委員会の開催について】
- 開催頻度: 年に2回 (夏と冬)
- 委員の構成: 半数以上の外部委員と,中核機関及び連携機関の代表から構成する。
- 令和6年度(2024年度)の課題選択委員
| 委員 | 名前 (五十音順) | 所属 |
| 外部委員 (9名) |
伊藤 公輝 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター 放射線診断科 | 浦野 泰照 | 東京大学大学院薬学系研究科 生体物理医学専攻 医用生体工学講座 生体情報学分野 | 小川 数馬 | 金沢大学新学術創成研究機構 革新的統合バイオ研究コア創薬分子プローブ研究ユニット | 小林 奈通子 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 放射線植物生理学研究室 | 志賀 哲 | 福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター・先端臨床研究センター 福島県立医科大学病院・核医学科 | 島添 健次 | 東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 | 塚田 祥文 | 福島大学 環境放射能研究所 | 脇谷 雄一郎 | (公社)日本アイソトープ協会 川崎技術センター | 鷲山 幸信 | 福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター 先端臨床研究センター |
| 内部委員 (7名) |
石岡 典子 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(高崎量子技術基盤研究所)量子バイオ基盤研究部 | 菊永 英寿 | 東北大学先端量子ビーム科学研究センター | 永津 弘太朗 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 本部 | 豊嶋 厚史 | 大阪大学放射線科学基盤機構 | 羽場 宏光 | 国立研究開発法人 理化学研究所 仁科加速器研究センター | 福田 光宏 | 大阪大学核物理研究センター | 渡部 浩司 | 東北大学先端量子ビーム科学研究センター |
【課題選択の方法】
- 原則,書類審査と事前質問への回答などを基に課題選択委員会で合議により審査を行う。
- 必要に応じてヒアリングを実施する。
| ※ | ヒアリングは,原則,実験申込責任者または代理者に出席を依頼する。やむを得ない事情により出席できない場合には,インターネットを介したヒアリングなどを実施する。 |
【審査基準と評価方法】
- 学術的な重要性と課題の実行可能性を基準にして支援課題を選定
- 科学的評価の基準
- a) 学術的な重要性・妥当性
- 学術的或いは社会的な背景(国内外の研究動向,社会的な要請,研究の位置づけなど)を踏まえて,短寿命RIを利用した研究の特色・独創性・必要性,他の研究手法に対する優位性などを評価
- b) 研究計画・方法の妥当性
- 研究全体の計画性,供給を希望するRIの必要性(他の同位体では不都合な理由など),希望供給回数と数量の妥当性,RIの利用方法などを評価
- 技術的評価の基準
- RI供給の技術的な適合性,RI利用の安全性など